🎬 基本情報
- 原題:CODA
- 邦題:コーダ 愛のうた
- 公開年:2021年
- 監督:シアン・ヘダー
- 出演:エミリア・ジョーンズ、トロイ・コッツァー、マーリー・マトリン、ダニエル・デュラント、フェルディア・ウォルシュ=ピーロ
- ジャンル:ヒューマンドラマ/音楽/青春
- 上映時間:112分
- 受賞歴:第94回アカデミー賞 作品賞・脚色賞・助演男優賞(トロイ・コッツァー)受賞
🕯 あらすじ(ネタバレなし)
アメリカの小さな港町に暮らす高校生ルビー(エミリア・ジョーンズ)は、家族の中で唯一の聴者。
彼女の両親と兄は耳が聞こえない“ろう者”で、家族が漁業を営む中、ルビーは通訳として重要な役割を担っていた。
しかし、歌うことが大好きなルビーは、学校の合唱クラブに入り、その才能を見いだされる。
音楽大学進学の夢が膨らむ一方で、家族はルビーなしでは生活や仕事に大きな支障が出る。
夢を追うか、家族を支えるか――。
ルビーは人生の大きな選択を迫られる。
🎭 キャラクターと演技
🔹 ルビー(エミリア・ジョーンズ)
家族のために自分を犠牲にしてきた少女。音楽という“声”を見つけ、初めて自分の人生を考えるようになる。エミリア・ジョーンズの自然体の演技と、歌声の美しさが心に響きます。
🔹 フランク(トロイ・コッツァー)
ルビーの父。豪快でチャーミング、そして深い愛情を持つキャラクター。アカデミー助演男優賞を受賞した演技は必見! コミカルでありながら、娘との会話シーンでは胸が熱くなる感動を生みます。
🔹 ジャッキー(マーリー・マトリン)
ルビーの母。家族の絆を何より大切にするが、娘の夢を理解できず葛藤する姿がリアル。マーリー・マトリンも実際のろう者であり、その存在感が作品にリアリティを与えています。
🔹 レオ(ダニエル・デュラント)
ルビーの兄。妹が家族の通訳を続けることに罪悪感を抱きつつも、不器用にしか支えられない。
🎥 監督・演出
シアン・ヘダー監督は、フランス映画『エール!』をリメイクしつつ、よりアメリカの文化や漁村のリアリティを加えました。
- ろう者のキャスティングに本物のろう俳優を起用し、リアリティを徹底
- 家族の会話は手話が中心で、音のない世界と音楽の世界のコントラストが鮮やか
- ラストの“音を消す演出”が圧巻で、観客にろう者の視点を疑似体験させる仕掛けが秀逸
🎯 テーマとメッセージ
- 家族の絆と自立の狭間
家族を支える責任と、自分の夢を追う自由。どちらが正しいとも言えない、普遍的なテーマが描かれています。 - 音のない世界と音楽の力
音楽を聴けない家族と、音楽で夢を追う娘。その対比が切なくも美しい。 - 多様性と理解
障害者と健常者という線引きを超えて、人間同士がどう支え合うかを問いかける作品です。
見どころ
- 音のある世界とない世界のコントラスト演出
この映画の最大の特徴は、音楽映画でありながら“無音”の時間がとても印象的に使われていることです。ルビーの家族は音が聞こえないため、観客は時折、彼らの視点に切り替えられ、音がすべて消えた無音状態を体験します。特に合唱の場面やオーディションの場面では、音楽の美しさと無音の対比が感情を揺さぶります。**音がないからこそ、家族にとって音楽はどんな存在なのか?**という問いが、観客自身に突きつけられるのです。 - 家族のリアルで温かいやり取り
家族がろう者であることは特殊ですが、描かれるのはごく普通の家族の姿です。ルビーの母がちょっとお節介だったり、父がジョークを飛ばして笑わせたり、兄が思春期らしい反抗心を持っていたり――家族だからこその距離感や衝突、でも根底には深い愛情がある。こうしたリアルな家庭の空気感が、映画を特別な“障害の物語”にしないで、普遍的な家族ドラマとして成立させています。 - ルビーの成長物語としての魅力
この映画は家族ドラマであると同時に、1人の少女が夢を見つけ、自分の人生を選ぶ成長の物語でもあります。ルビーはこれまで“家族の通訳”という役割に縛られてきましたが、歌うことを通して初めて「自分はどう生きたいか」を考えます。この“自分のために生きる”ことへの葛藤が、若者の自立を描く青春映画としても心に響きます。 - 圧巻の音楽シーンと歌声の力
ルビーが合唱クラブで歌うシーンや、オーディションで披露する「Both Sides Now」はまさに鳥肌モノ。エミリア・ジョーンズ自身が歌っており、その伸びやかで切ない歌声は、家族への想いと夢への情熱がすべて込められています。歌声が家族に届かない切なさと、それでも歌いたい気持ちが交錯する瞬間は、この映画の核心ともいえる見どころです。 - トロイ・コッツァーの演技とユーモア
父フランクを演じたトロイ・コッツァーは、ろう者の俳優として初めてアカデミー賞助演男優賞を受賞しました。彼の演技はコミカルでチャーミング、でも娘を思う父の愛情が滲み出ています。特に“歌声を感じたい”とルビーの喉に手を当てるシーンは、言葉以上に心が伝わる名場面。泣けるだけじゃなく、笑いもあって、家族の温かさがよりリアルに感じられます。 - 多様性と社会的テーマの自然な描き方
この作品はろう者の家族を描いていますが、障害を“悲劇”や“特別なもの”として扱いません。むしろ、彼らが日常生活をどう楽しみ、どう苦労しているかを自然に描くことで、多様性の大切さや理解の必要性をさりげなく伝えています。説教臭くなく、でもしっかり心に残る描き方が秀逸です。
📝 まとめの感想(詳しく)
『コーダ 愛のうた』は、一言で言えば家族の絆と夢の狭間で揺れる少女の成長物語ですが、その描き方がとても繊細で普遍的だからこそ、誰の心にも届く映画だと思います。
この物語で印象的なのは、“家族のために生きること”と“自分のために生きること”が必ずしも両立しないという現実です。ルビーは家族を愛しているし、家族もルビーを大切に思っています。でも、だからこそ、彼女が夢を追うことで家族を置き去りにしてしまうような罪悪感が生まれる。これは、障害のある家族を持つ子供だから特別というより、誰もが親元を離れるときに感じる普遍的な葛藤だと言えます。
また、音楽というテーマの扱い方も見事です。ルビーの家族は音楽を理解できません。彼女が歌っても、ただ口が動いているだけに見える。でもルビーが歌うのは、家族に自分の心を伝えたいからであり、歌声が届かない切なさが、映画全体を優しい悲しみで包み込みます。そして、その悲しみを乗り越えるのが、あのラストのオーディションシーン。音が消えた瞬間、観客は家族の視点を疑似体験し、“音楽が聴こえないのに、娘の夢を応援する”という家族の愛情の深さに気づかされます。
父フランクがルビーの喉に手を当て、振動で彼女の歌を“感じる”シーンは、この映画を象徴する瞬間です。言葉や耳がなくても、心は繋がる。家族の絆は、音や言語を超えて存在するものだと教えてくれます。
さらに、この映画は障害を悲劇として扱わないのも素晴らしい点です。ルビーの家族は不便を感じながらも、ユーモアとたくましさで日常を生きています。彼らが音楽の価値を理解できなくても、娘を愛する気持ちは変わらない。障害を“特別視”しすぎるのではなく、多様な生き方のひとつとして自然に描くことで、観客の心に優しく響きます。
作品賞を受賞したのも納得で、重いテーマを扱いながらも、観た後に心が温かくなる映画です。感動の涙が流れるけれど、それは悲しい涙ではなく、「家族っていいな」「夢を追うことは尊いな」と思える前向きな涙です。
『コーダ 愛のうた』は、障害者と健常者の話でもあり、親子の話でもあり、そして何より“自分の声を見つける”話です。だからこそ、年齢や立場に関係なく誰にでも響く作品だと思います。見終わったあと、きっと自分の家族のことや、自分が大切にしている夢のことを考えたくなるでしょう。
家族を大切に思う人、夢に挑戦したい人、そして音楽を愛するすべての人におすすめしたい映画です。
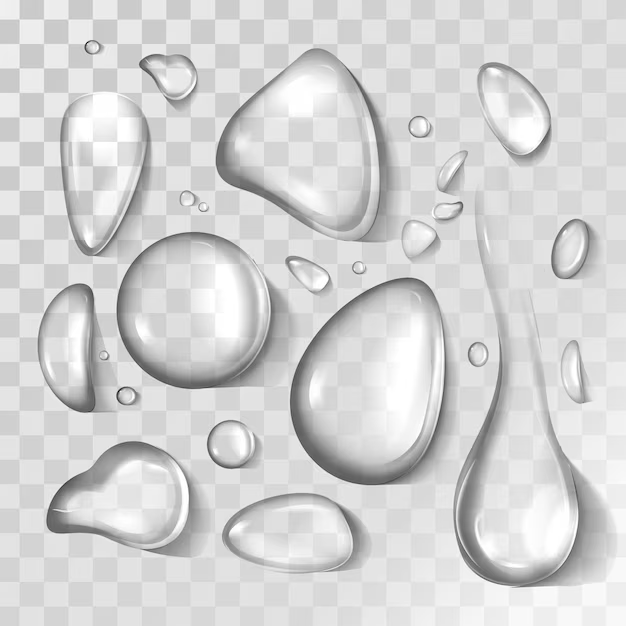


コメント